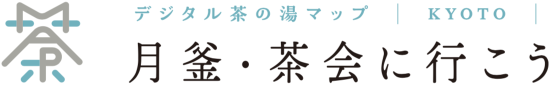
初めてお茶会に参加することになった場合、多くの人が心配になるのが、「どんな服装で行けばよいのだろう」「何を持っていけばよいのだろう」ということではないでしょうか。せっかくお茶会に参加するのに「こんな服装で失礼はないだろうか」「マナー違反なことをしていないだろうか」「何か特別な持ち物が必要なのでは」などと、いろいろな不安が頭をよぎるところだと思います。そんな心配をなくすように、こちらの記事では、茶道関連の書籍や雑誌を出版している淡交社が、お茶会に出席する際にふさわしい服装や必要になる持ち物について解説します。初めてお茶会に出席する方は、ぜひ参考にしてください。
そもそもお茶会とは、どういった会なのでしょうか。簡単に言えば、亭主(席主)がお客様をお招きし、お菓子とお茶でおもてなしするのがお茶会です。少人数で催し、料理もふるまう「茶事」、大人数のお客様を招く「大寄せ(おおよせ)茶会」など、いろいろなパターンがあります。茶道は一つ一つの所作に意味があり、決まった作法でお茶を点て、お客様に振る舞いますが、それだけではありません。亭主はその時のお茶会のテーマに合わせて道具類を選び、お客様が心地よく過ごせる空間になるよう、茶室全体の雰囲気にも気を配るなど、お客様をもてなすため、お茶会全体を演出することに心を砕きます。
お客様としてお茶会に参加した場合、正式な服装は着物(和服)です。ただし、おおかたの「大寄せ茶会」の場合は洋服でも構いません。初めて参加するのは、大寄せ茶会のケースが多いと思いますので、まずは洋服でお茶会に参加する際のポイントをまとめておきましょう。
洋服の場合、男性はスーツがふさわしいです。女性はワンピースやブラウスなどであれば問題ありません。上下とも身幅に余裕があると動きやすく、正座もしやすいです。ただし、いずれも華美な色やデザイン、柄のものや、肌の露出の多いものは避け、所作に適した装いを心掛けるようにしましょう。女性の場合、パンツでもスカートでも構いませんが、スカートの丈は正座した時に膝が隠れるぐらいだと安心です。トップスはお辞儀をした時に胸元が開きすぎないものを選びましょう。白い靴下を忘れないように。必ず持参して、茶室に入る前に履くようにします。
お茶会にふさわしい服装では、清潔感が最も重要なポイントです。爪は清潔にして、きれいに切っておくこと。マニキュアは落としていった方がベターです。ネイルは外しておきましょう。繊細な漆器や布の道具を使いますから、長い爪や飾りがついたネイルは引っかかったりする可能性があるので避けます。このほか指輪や腕時計、ネックレス、カフスなどは外しておくのが基本です。茶器などに傷をつけないようにするためです。
髪が長い方は、結んでまとめておきましょう。お辞儀をしたり礼をしたりする時に髪が前に落ちてきて顔にかからないようにしましょう。お化粧は決して派手にならないように。特に口紅は茶碗に着くと取れにくいので、控えるようにしましょう。香水などはつけないのが原則です。
初めてのお茶会といっても、普段から着物を着慣れている方はぜひ、着物で参加してみましょう。
男性は着物を帯で結び、袴を身に着けるのが茶席での正式な服装です。女性は着物に帯揚げと帯締めを使って帯を結びます。着物は場所によって小紋、色無地、訪問着などふさわしいものを選ぶようにしましょう。着物のすぐ下に着る長襦袢(ながじゅばん)の半衿は無地で、男性の場合は着物と同系色のもの、女性は白色が望ましいです。男性の帯は角帯が一般的、女性の帯は名古屋帯または袋帯で、結び方は「お太鼓結び」が適しています。着物の場合も洋服と同じで派手な色や柄、または浴衣のような簡略すぎるものはお茶会には不向きです。
足袋は白足袋で。茶室で履き替えるために、一足持参しましょう。
洋服の時と同様、髪が長い方は結んでまとめておきましょう。髪飾りをつけることも禁物です。
お茶会に招待された際、何を持参すればよいのでしょう。お茶会に参加するには、以下の5つの道具が必要になります。
初めてのお茶会に必要な持ち物として、懐紙や扇子、足袋など基本の道具について解説します。
和紙の束を二つ折りにしたものです。基本的には真っ白なものを使い、お菓子を取って、この上に載せていただきます。口元や指が汚れた時、軽くふき取ることにも使うことができます。男性用と女性用で大きさが異なり、男性用のほうが少し大きめです。1セットを「一帖」(いちじょう)と呼びます。
主菓子をいただく時には一口で食べず、一口のサイズに切って食べます。本来はクロモジという植物(クスノキ科)を原材料とする木製の楊枝「黒文字」を用いますが、それが出されない場合はステンレス製や銀製、プラスチック製の菓子楊枝(菓子切)を使います。使い終われば懐紙で拭き取り、帰宅後は洗って清潔にして、楊枝入れに戻します。
正座して挨拶する時のほか、床の間や道具を拝見する時などに、膝の前に置いて使います。茶室では儀礼的な役割を持っており、結界の代わりとなるもので、相手や茶道具に対して一線を画し、謙虚な気持ちを表します。扇面を広げることはありません。茶道では一般の扇子よりも一回り小さいものを使います。また、男性用と女性用で大きさが異なり、男性用のほうが少し大きめです。
茶会に参加するのに必要な持ち物一式を入れる袋です。数寄屋袋(すきやぶくろ)と、ひと回り小さい帛紗(ふくさ)ばさみがあります。
着物の場合は足袋、洋服の場合は白色の靴下を履きます。茶室の中を清潔に保つために、茶室に入る前に履き替えます。
亭主が心を砕いて準備したお茶会に参加する際、客として心得ておきたいことがらがあります。同席するお客さんが気持ちよく過ごせるように以下5つの点に注意しましょう。
男女とも清潔感のある装いを心掛け、華美な色やデザイン、柄のものや、肌の露出の多いものは避ける。
茶器に傷をつけないために、指輪、腕時計、ネックレス、カフスなど装飾品は外しておく。
爪は切り、茶道では、漆器や布の道具を使います。長い爪だと引っかかったりする恐れがあるので、ネイルは外しておく。また、マニキュアも落としておくことを忘れずに。ハンドクリームもつけない方がベターです。
茶会では何度も礼をします。その際、髪が前に落ちてきて顔にかからないようにするため、髪が長い方は、結んでまとめておく。
お化粧、特に口紅などは控えめに。茶碗に着くと落ちにくいので。香水などは避ける。髪飾りもつけない。髪から外れて落としたりすると道具に傷をつけたりする恐れがあるためです。
お茶会は特別な場ですが、事前にポイントを押さえておけば安心して楽しむことができます。ぜひ、この記事を参考にして進めてください。初めてのお茶会が素敵な思い出となりますように。