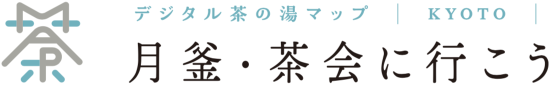
千利休(1522~91)という歴史上の人物の名前を聞いたことがある人は多いでしょう。現代にも続く茶の湯(茶道)を大成させた戦国時代の茶人です。織田信長や豊臣秀吉に仕え、数多くの茶人に影響を与えました。「日本文化の総合芸術」とも言われる茶道の基礎を築いたと評価される人物から学ぶべきこととは、どんなことなのでしょうか。こちらの記事では、茶道関連の書籍や雑誌を出版している淡交社が、千利休の生涯と、その功績について解説します。千利休を通して茶道をより詳しく知りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
千利休は茶人でありながら波乱万丈の生涯を送りました。その生涯をたどってみましょう。
利休は大永2年(1522年)、和泉国堺今市町(現在の堺市)の商人の家庭に生まれました。幼名は与四郎といいます。堺の豪商・茶人の武野紹鷗らに茶の湯の教えを受けました。記録に残る初茶会は23歳だった天正13年(1544年)。織田信長、続いて豊臣秀吉の大きな信頼を得て、それぞれの茶頭を務めました。天正13年(1585年)の禁中茶会に際して、正親町天皇から「利休」の居士号を賜りました。一畳半座敷、二畳茶室の茶室「待庵」(たいあん、国宝)などを築き、茶碗など茶道具の取り上げなどから、茶の湯における「わび」の美意識を極めたとされます。「利休七哲」と呼ばれる武家茶人のほか、数多くの弟子がいたとされ、現代に至る茶の湯の基礎を築きました。天正19年(1591年)、秀吉の命により切腹。その原因については諸説あります。
|
1522年 大永2年 |
・和泉国堺今市町(現在の堺市)の商人の家庭に生まれる。幼名は与四郎 |
|
1538年 天文7年 |
・この頃から堺の茶人、北向道陳に茶の湯を学ぶ |
| 1540年 天文9年 | ・堺の豪商・茶人、武野紹鷗に茶の湯を学ぶ |
| 1544年 天文13年 |
・初めての茶会に奈良の富商・茶人、松屋久政らを招く。珠光茶碗や香炉を用いる |
| 1555年 弘治元年 |
・茶会に紹鷗のほか、堺の豪商、今井宗久らを招く |
| 1573年 天正元年 |
・信長の妙覚寺茶会で濃茶を点てる |
|
1574年 天正2年 |
・信長の相国寺茶会で堺の豪商、津田宗及らとともに千鳥の香炉を拝見 ・信長の相国寺茶会で宗及とともに名香・蘭奢待を拝領する |
|
1575年 天正3年 |
・朝倉攻めの信長に鉄砲玉を送り、その礼状を送られる ・信長の妙覚寺茶会で茶頭を務める |
| 1582年 天正10年 |
・宗久、宗及らとともに信長の安土城に新年の参賀をする |
| 1583年 天正11年 |
・豊臣秀吉の坂本城茶会で茶頭を務める |
| 1584年 天正12年 |
・大坂城山里の座敷披きの茶会に参列 |
| 1585年 天正13年 |
・秀吉の有馬湯治に同行、茶会を催す |
| 1587年 天正15年 |
・九州出陣前の大坂城大茶会で一席を担当する |
| 1589年 天正17年 |
・大徳寺聚光院に永代供養料を寄進 |
| 1590年 天正18年 |
・秀吉の小田原征討に従軍 |
| 1591年 天正19年 |
・秀吉の命により堺に蟄居 |
千利休が茶道を通じて説いた教えとは、どういうものなのでしょうか。
利休は、日本独特の美意識「わび」の精神を茶の湯で確立させたと言われます。慎ましく、簡素でありながら清らかな精神を尊重する。その志向は、彼が建てた茶室や重宝した道具などから伺うことができます。
また、利休が茶道について説いたとして伝わる「四規七則」という言葉からは、利休の教えの本質が浮かび上がります。
「四規七則」のうち「四規」とは、茶道の精神を表した「和敬清寂(わけいせいじゃく)」という四文字の言葉を指します。この四つの文字には、茶道のすべての心が込められているといわれています。
「和」とは、互いに心を開いて仲良くするということです。相手と心を合わせ、理解しようとする意識のことであり、他者と共によく生きようとする心が大切だということを説いています。
「敬」とは、互いを敬いあうということです。その根本には自分自身を大切にするという意識があります。他者も同じように自分を大切にしているということを認識することで、他者を尊重できるようになるのです。
「清」とは、目に見えるだけではなく、心の中までも清らかであるということです。形として現れない汚れは分かりにくく、かつ簡単に落とせないものでもあります。
「寂」とは、どんな時にも動じない心のことです。心のゆとりを持つためには、日ごろの修練が必要です。
続いて「七則」とは、茶人が心に留めるべき心得を説いたものです。「茶の湯とは何ですか」と弟子から問われた千利休は「この七則がすべてです」と答えたと言われます。
「茶は服のよきように点て」は、自分の理想の追求ではなく、相手のことを考えて取り組むことの大切さを説いています。気配りや心配りすることが大事だということを意味しており、一生懸命に点てたお茶を、客がその気持ちも味わっていただけるように、心をこめて、お茶をおいしく点てるということが求められます。
「炭は湯のわくように置き」は、試行錯誤して物事の本質をよく見極めることが大切だという意味です。炭に火をつけさえすれば必ずお湯が沸くとは限りません。お湯がきちんと沸くように火を熾すには、上手な炭のつぎ方があります。しかし、型どおりにするだけでは火はつきません。工夫し、想像力を働かせることが求められます。
茶道では季節感をとても重んじます。その中で、相手への思いやりや工夫する気持ちをもって対応することを説いているのが、「夏は涼しく冬は暖かに」です。相手のことを思い、最適な方法を考えて、きめ細やかに対応することが大切です。
「花は野にあるように」は、花を自然にあった状態で再現するということではありません。野に咲く美しさと自然から与えられたいのちの尊さを、一輪の花に盛りこむことを意味しています。少ない要素で野を思い起こさせる。つまり、飾らず、本質を際立たせることの大事さを説明しています。
「刻限は早めに」は「時間はゆとりを持って、早めに」との意味です。時間にゆとりを持つことで心に余裕ができ、その結果、相手にも行き届いた配慮ができます。相手の時間を大切にすることにもつながります。
「降らずとも雨の用意」は、起こりうる事態を想定して、備えの準備をすることの大切さを説いています。それは、自分自身の不安をなくすと同時に、相手の不安を取り払うことにもなります。どんな時も適切に対応できるようにするには、柔軟な心を持っていることも求められます。
「相客」とは、一緒に茶席に着いたお客さんの意味です。「相客に心せよ」は、正客(しょうきゃく)も末客(まっきゃく)も、お互いを尊重しあい、理解を図り、気持ちを通じ合わせることの大切さを説いています。
利休のその波乱万丈の生涯で、数多くの茶人に影響を与えました。同時に、歴史上の人物も多数登場します。
織田信長(1534~1582) 戦国武将。天下統一を目前に本能寺の変で明智光秀に攻められ、倒れました。
信長と利休の出会いは明確にはわかりませんが、「今井宗久茶湯書抜」に元亀元年(1570年)、利休が信長の前で茶を点てたという件があるといいます。一方で、越前出陣中の信長に利休が鉄砲玉を送ったというエピソードも残ります。
信長は室町将軍家の名物茶道具を強制的に買い上げる「名物狩」を行いました。戦功のあった武将にはこれらを下賜し、茶会を開くことを許可するという政策「御茶湯御政道」を敷いたことで、武士の間で茶の湯の価値が高めることにつながったとも言われます。
豊臣秀吉(1536~1598) 言わずと知れた戦国時代に天下統一を成し遂げた武将。関白・太政大臣。
信長亡き後、利休が茶頭として仕えたのが、豊臣秀吉です。大勢の人々を集めて数々の大規模な茶会を開き、利休を重用しました。天正13年(1585年)の禁中茶会では黄金の茶室を披露しました。天正15年(1587年)には九州征討を記念して北野大茶湯を開催。身分を問わず大勢の人が全国から集いました。
天正19年(1591年)、秀吉は利休に堺への蟄居を言い渡した後、切腹を命じました。秀吉が利休に切腹を命じた真相は、いまだ不明です。
古田織部(1543~1615) 大名茶人。信長、秀吉に仕える中、利休と交流し、親交を深めました。師弟として強い結びつきを感じさせる手紙が残されています。一方で、整った美を極める利休に対し、「織部焼」から感じられるような斬新さを好むなど、志向は利休とは大きな違いを見せました。大坂夏の陣で陰謀を疑われ、幽閉され自害しました。
細川三斎(1563~1645) 豊前小倉藩主、肥後八代藩主。細川幽斎の長男。千利休の茶の湯に親しみ、利休が堺に蟄居する際、古田織部と一緒に見送ったことで知られます。利休の教えを忠実に守る茶風については「細川三斎茶書」などに伺えます。利休が愛した石灯籠が自分の墓碑となっています。
織田有楽(1547~1621) 戦国武将、織田信長の弟。秀吉も一目を置いた茶の湯巧者でした。元和3年(1617年)に建仁寺の正伝庵を再興、茶室「如庵」を作って隠居しました。
今も残る千利休ゆかりの地をご紹介しましょう。京都では以下の場所が代表的です。
聚光院は、臨済宗大徳寺派の大本山、龍宝山大徳寺の塔頭です。京都市北部の紫野に位置する大徳寺の境内にあります。利休の墓があるほか、茶道・三千家の菩提寺でもあり、茶道とは深い縁を持っています。利休の月命日である毎月28日には現在も三千家により「利休忌」が営まれます。
戦国時代の永禄9年(1566年)、武将・三好義継が義父の長慶を弔うために建立しました。
寺は通常非公開ですが、本堂南側に広がる枯山水の庭園「百積庭」(国指定名勝)や、茶室「閑隠席」「枡床席」(いずれも重要文化財)など、数々の文化財を擁していることで知られます。本堂の中心・室中を囲む16面の襖に描かれた狩野永徳による障壁画「花鳥図」(国宝)は何とも圧巻です。室中奥の仏間には利休の木像が鎮座しています。
※京都市北区紫野大徳寺町58
天正15年(1587年)、豊臣秀吉が主催して北野天満宮で北野大茶湯が開かれました。利休らが茶を点て、多くの参加者でにぎわいました。境内には「北野大茶湯之址」の碑が建てられているほか、茶の湯の水を汲んだと伝わる太閤井戸も残っています。
全国約1万2000ある天満宮、天神社の総本社で、御祭神は菅原道真公。天暦元年(947年)、御神託により創建されました。学問や芸能の神様として知られているほか、災難厄除けなどに御神徳があるとして広く信仰されています。国宝「北野天神縁起絵巻 承久本」をはじめ文化財を数多く所蔵しているほか、梅や紅葉の名所としても知られています。
※京都市上京区馬喰町
平安時代の陰陽師、安倍晴明公を祭る晴明神社。京都市内を南北に走る堀川通に面したその境内には「千利休居士聚楽屋敷趾」と刻まれた石碑が建てられています。「晴明井」と呼ばれる井戸があり、利休はその水を使って茶を点てたと伝えられます。
寛弘4年(1007年)、晴明公が仕えていた一条天皇の命を受けて創建。小説や漫画などのモデルとしておなじみの晴明公は、皇族から貴族、庶民に至るまで広く、悩みや苦しみを取り除いたとされることから、「魔除け」「厄除け」の神社とも言われます。
※京都市上京区晴明町806
利休が豊臣秀吉の怒りを買い、大徳寺山門にあった利休像は磔にされました。その場所が戻橋です。堀川にかかる長さ約11メートルのこの橋は、晴明神社から南へ約100メートルのところにあります。
時は平安時代。父の葬列に駆けつけた息子が、この橋の上で柩にすがってお祈りしたところ父が蘇生したといわれます。そんな伝説が橋の名前の由来になっています。
※京都市上京区堀川下之町
数奇な人生をたどった利休ですが、茶の湯を通じて彼が説いた心は今も様々な場面で生きることは間違いありません。ぜひ、この記事を参考にして、茶道を体験する際などに利休が目指した茶の湯の姿に思いを馳せていただければと思います。